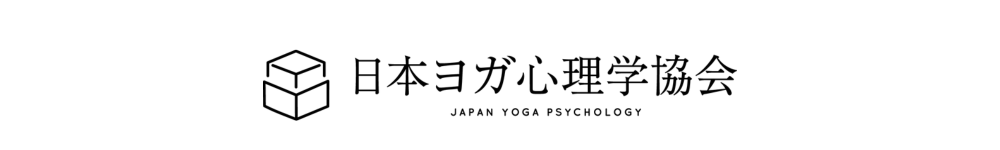心理学講師SATORUです。日本ヨガ心理学協会代表をつとめております。
病気は心がつくる?
原因不明の病気が「メンタル(心)から来ている」と言われることは聞いたことありませんか?
しかし、病気や不調が心から来ているのか、単に原因が解明できないのかは誰にも確証できるものではありません。
ただ、もしその病気が心から来ているのだとしたら、逆に言うと、心に変化があれば病気も収まる可能性があるのではないでしょうか。

心が病気を作る例

例えば、ある人の心の奥底で「私は幸せになってはいけない、どこか苦労や不幸を背負うべきだ」という価値観の人がいます。
その場合、努力して幸せな生活を手に入れたとしても、心の奥の思いが体に影響し、病気として現れるという説があります。
本人でさえ気づかない心の奥の思いが、身体の症状に影響している場合があります。
心が病気を作るメカニズム

「身体と心は一つ」と聞いたことはありませんか?心と体は深く結びついています。
そういうと怪しいとか、スピリチュアル系だと言う人がいますが、果たしてそうでしょうか?
人間はストレスや強い負の感情が長く続くと、自律神経や免疫系に影響し、体調不良や慢性的な症状が出ることがあります。
ストレスが溜まると胃潰瘍になる。
これは一般的に受け入れられている理論ですよね?
その胃潰瘍を改善するには、もちろん身体にアプローチする薬や治療は大事ですが、
それがストレス(心)から来ているのであれば、心の状態が変わると、胃潰瘍も改善に向かう可能性があります。
こうやって考えると何も 不自然では無いですよね?
参考理論
・『The Body Keeps the Score(邦題:心と身体が記憶するトラウマ)』
・ゲシュタルト心理学
・ポリベーガル理論
・アダルトチルドレン理論
詳しく学びたい方は「心と身体のつながりをヨガと心理学の視点から解説」を参照してください。
心が病気を作ると言うのは何もスピリチュアルな話ではない

これは決してスピリチュアルな話ではなく、心理学や生理学の研究でも心と身体の相互作用は知られています。
論理的な話はたくさんありますが、特に森田療法の理論が理解しやすいのではないかと考えています。
森田療法とは
日本で生まれた心理療法で、「不安や症状をなくすのではなく、あるがままに扱いながら生活を回復させていく」と言う考え方に基づいています。この記事では概要だけ紹介していますが、後日詳しい解説記事も公開予定です。
その他、プラシーボ効果やポリヴェーガル理論、ベッセル・ヴァン・ディアコークの理論などがあります。ここでは話を端的にするために割愛するので、関心がある方は別記事を参照してください。
確固たるエビデンスはどこまでいってもない
それでも、「心が病気を作る」という理論について世の中の誰もが納得するようなエビデンスを出す事は不可能です。
そういった方は、10年後か100年後かエビデンスが確固たるものになるまで、この理論を信用しなければいいだけの話です。
※この記事は医療行為を示すものではありません。誤解のないように。
\ 「身体と心」についての知識を無料公開しています /
心を変容するための方法
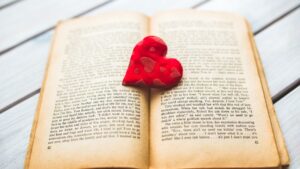
心はどうすれば変わるのか。特に心といっても、「無意識」が体に影響しやすいと言われています。
無意識とは簡単にいうと自分でも気づいていない心の奥の部分です。自分でも気づいていないところなので。どのようにすれば変わるのかというのはこれもまた、誰も確固たる答えを持っていません。
こうだと言い切る人はいますが、それでも確実な手法など持ってる人はこの世にいないことはご了承ください。 その上で、日本ヨガ心理学協会で定めているところを紹介します。

心と身体のつながりを知る必要性

心の仕組みを学ぶことが大切です。心理学を学ぶことや、心のうちをシェアできる仲間を作ることも必要です。
そして、心と身体のつながりを学んで、五感でそれを感じることもお勧めします。
自分の本心を知る必要性

抑圧された感情が腰痛になるという考え方もあるのをご存知ですか?
自分が何かの感情に蓋をしていると、腰痛になるという考え方です。(他の不調や不具合も同じかもしれません。)
そのためにもまず、自分がどんな気持ちがあるのか、本心と向き合うことが大切です。
アダルトチルドレンの理論でも、アダルトチルドレンは何らかの身体の不調を抱えているケースが多いと言われています。
\ 「身体と心」についての知識を無料公開しています /
感情に気づき癒す必要性

上記と似ているようですが、何を「感じているか」というのはまた違った角度からのアプローチです。
感情について。よく受講者さんらに「あなたは今、どんな感情ですか?」と聞くと、
「〇〇って重要だなと思いました。」などと返ってきますが、これは感情ではありません。
感情とはもっと、感覚的なことで、どのように感じたか?です。これは日頃から五感を研ぎ澄ますトレーニングが必要であると考えます。
手放すことも必要

手放す、というと諦めるというイメージかもしれませんが、そうではありません。
自分の中の何かが自分を苦しめている時、その苦しみを解決しようとすることも良いのですが、一方で、「手放してしまう」ことも一つの方法です。
最終目的は、解決ではなく、あなたの心が幸せになる道を選べるかどうかです。
上記はシンプルにまとめましたが、それを上っ面の知識でなく、身体ごと本気で、心の底から思えるかということです。
具体的な知識やワーク
協会で実践している代表的な紹介です。
ヨガ

ヨガというと、一般的にはフィットネスやダイエットのように思っている方も少なくないでしょう。しかし、必要なのは、固まった身体をほぐすことと、五感を敏感にして自分の体感覚を取り戻すことです。
難しいポーズを取るための練習をするわけではありません。
五感を研ぎ澄ませるのがヨガの役割です。
瞑想

これもよく誤解されますが、無心になるとか、悟りを開くために行うものでもないです。足が痛いのに座り続けるものでもありません。
ただただ、特に何もせずに座って呼吸の音を聞いたりするだけの「余白」のような時間を持つことです。
「余白」は心にとってとても大切です。
呼吸法

自分の身体の深部の感覚を感じながら、深呼吸をすることは心の奥にアプローチすることになります。これはヨガの考え方でもあります。
また、深呼吸は単なる空気のやり取りではなく、遠い記憶にもつながっていますし、心の縛りを緩めることにもなります。
エンプティチェア

エンプティチェアとは、空の椅子を相手に見立てて気持ちを言葉にする心理療法です。
実際に相手を目の前に出すのではなく、椅子を使うことで自分の内側の感情が浮かび上がりやすくなります。
抑え込んでいた本音を安全に整理し、心の負担を軽くするためのワークです。
箱庭療法

箱庭療法とは、小さな砂箱の中に人形やオブジェを置いて、自分の内側にある感情や無意識の状態を“形”として表す心理療法です。
言葉では言いにくい気持ちが自然に現れやすく、心の奥にあるテーマを安全に見つめることができます。
表現された世界を一緒に見ていくことで、気づきや心の整理が進み、身体の不調につながるストレスの根本にアプローチすることができます。
カウンセリング

カウンセリングとは、自分では気づきにくい心の状態や思い込みを、専門家との対話を通して整理していく方法です。
話すことで感情がほどけ、抱えていたストレスや無意識のパターンが明確になり、身体の不調につながる心の負担が軽くなる場合があります。
解決を押し付けられる場ではなく、「本心に気づくための安全な対話の場」と考えてください。
オンラインでの心理学の学び

心の学びは、特別なときだけ行うものではなく、日々の生活に寄り添う形で続けることが大切です。オンラインでつながることで、遠く離れた仲間や講師とも気軽に交流でき、無理なく・自分のペースで・楽しく学び続けることができます。
参考
\ まず無料で学んでみたい方へ /
リトリートについて
知識的なことは日々のオンラインで学べますが、リアルでないとできないことはリトリートで行っています。
リトリートとは、一定期間の間、山梨県北杜市白州町の森の中で仲間と共に過ごす、自分と向き合うための時間のことです。
人生の時間を止めて、じっくりと自分と向き合い心の奥の声を聞く機会です。そんな時間が足りないと思った方は、ぜひご参加ください。
真剣に楽しく、ご参加されたい方なら、ヨガ歴や心理学の予備知識もいりません。
心の縛りを解くための体験型ワーク
リトリート(一部オンライン講座)で行うことができます。例えば、
- 過去の自分に「もう怖がらなくていいよ」とメッセージを送るワーク
- 幼少期の母に会い、心の奥で話すワーク
これらのワークは素晴らしいものですが、ポイントは「臨場感を持って、本気でイメージする」ことです。本当にその場でやり取りしているように体験できるかどうかが重要です。
この臨場感は頭で考えるものではなく、体感覚が関わってきます。
私たち日本ヨガ心理学協会では身体を通してリアルな体験を提供することに特化しています。
注意点
- 過度な期待は禁物です。参加すれば病気が治る、といったことは誰も断言できません。
- あくまで心と体のつながりを体験し、自分自身と向き合う機会としてご活用ください。
最後に
今、私たち日本ヨガ心理学協会では、心と体のつながりを体験できるリトリートを開催しています。
あなた自身が心の縛りを感じているなら、その縛りを解く作業が必要です。ワークを通して、過去の自分や大切な人にメッセージを送ることで、心を解放することができます。ポイントは、本気で心を動かすこと、臨場感を持って体験することです。
ただし、過度な期待はしないでください。参加すれば病気や不調が治る、など誰も断言できるものではありません。
それでも、自分の体を通して、自分の心と向き合ってみたいという方には、ぜひご参加をお待ちしています。
\ 心と身体のつながりを無料で学ぶ /